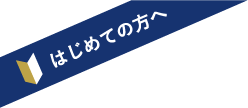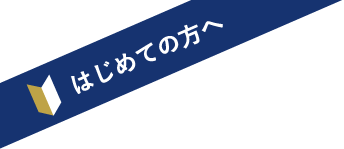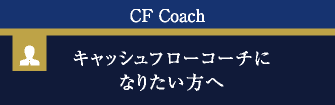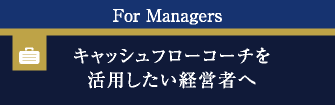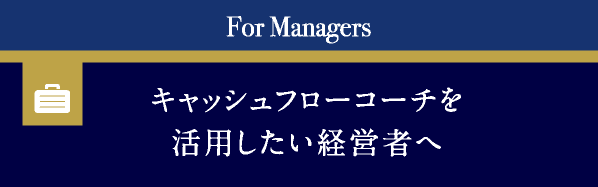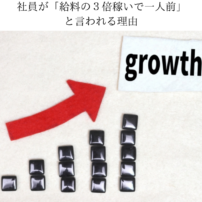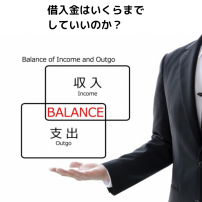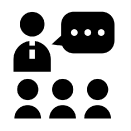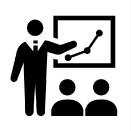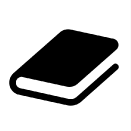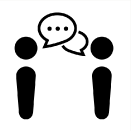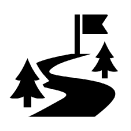診療時間を割いてミーティングをする経済効果の考え方。機会利益の発想と、その回収方法を言語化する!
2025.10.15 執筆者:和仁 達也![]() キャッシュフローコーチキャッシュフロー経営着眼点
キャッシュフローコーチキャッシュフロー経営着眼点
定例ミーティングの価値は過小評価されがちです。
「目先の売上にしばられず、定例ミーティングを行うことで
どれだけの経済効果があるか」を、歯科医院を題材に
シミュレーションしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホワイト歯科では、勤務医の突然の退職に伴い
院内の基盤を整え直すことを決めた。
具体的には毎月1回、午後4時間を院内ミーティングに充てるというものだ。
それによってスタッフ間の意思疎通を図りやすくなり、
院長もスタッフとの懇親が深められ風通しが良くなる効果が期待できる。
さらに患者情報の申し送りをそこでしたり、
トップ衛生士の深い考察力や考え方、そして仕事のスタンスを
他のスタッフにも見てもらうことで、医院全体の基準を
一段上に引き上げる効果を狙っている。
とは言え、月に一回、午後の半日間も診療を止めて
ミーティングをすると言うことは、相応の売上ダウンもあるだろう。
短期的には経営が厳しくなるかもしれない。
その点について経済面の判断をしたいと考え、今月の
キャッシュフローコーチの和仁とのミーティングのお題でそれを取り上げた。
事情を聞くとキャッシュフローコーチはいくつかの質問を投げかけた。
「忙しい時間を割いて定期的にミーティングをすると言うのは、
簡単なことではありませんね。
というのもミーティングをするための時間はタダではなく、
院長やスタッフの人件費と言うコストがかかっていますから。
これを【実質コスト】といいます。
そして実際にはそれだけではなく、もしその時間で診療をしていれば
得られたはずの売上や粗利を失うことも意味します。
これを【機会コスト】といいます。
ということは、意識する・しないにかかわらず、
ミーティングを行うからには、少なくとも実質コスト以上の価値を
生むことが求められますし、本来なら機会コスト以上の価値を
生むことを目指す必要があるでしょう。
では具体的に計算してみましょうか。
<実質コストの計算>
時給2千円のスタッフが6人、時給6千円の勤務医、
時給9千円の院長がミーティングに参加するとします。
もし4時間のミーティングを、診療時間を割いて行うとしたら、
そこにはいくらのコストがかかっているでしょうか?
①スタッフ→@2千円× 4時間× 6人= 4万8千円
②勤務医→@6千円× 4時間= 2万4千円
③院長→@9千円× 4時間= 3万6千円
合計10万8千円
<機会コストの計算>
チェアが4台あり、1台で1時間の売上が平均1万円、粗利率が80%とします。
この時、生まれる粗利はチェア1台で1時間あたり8千円。
それが4台で4時間なら、ミーティングの時間で生まれるはずの
粗利はこうなります。
@8千円× 4台× 4時間= 12万8千円
つまりミーティングをするのであれば、少なくとも10万8千円以上、
できることなら12万8千円の粗利を生むことを意識して、
準備をし、本番のミーティングを行いたいところですね」
加藤院長は、その数字を見て思わず唸った。
「なるほど、ミーティングにはコストがかかっていると
漠然と思っていましたが、普通に診療していれば得られたはずの
12万8千円の粗利を手放すわけですね。
これは相当な自覚を持ってミーティングをしなければ、、、」
キャッシュフローコーチは話を続けた。
「そうですね。そこで次に考えたいのは投資回収シナリオです。
このミーティングは、1回やって終わり、ではなく、
仮に月に1回を継続的に行っていくとすれば、
年間で120万円以上のコストをかけることになります。
機会コストで言えば150万円相当にもなるので、
そこだけを見れば、ミーティングよりも目先の診療を
優先したくなるのも無理はありません。
ただそれによって、院内のコミュニケーションが不足し、
教育や場づくりが先送りとなり、
人間関係のトラブルややりがいの低下などで
スタッフの離職や患者離れが起こり、
院長に過度なストレスがかかるとしたら、
それは放置できませんね。
そこで、投資回収シナリオとして考えられることを列挙してみましょう。
見えない形でそれらがいくらのコストになっていたのか、
を試算してみます。例えば次のように。
①人の採用コスト→1人30万円
②人の教育コスト→1人30万円(年間)
③伝達ミス等で生じる患者離れ→1人当たり粗利6千円×年4回の来院= 2万4千円
④トラブルで院長にかかるストレス→プライスレス
仮に、このような概算の設定があったとしましょう。
このとき、年間でスタッフが2人辞めて教育し直すとしたら、
採用コストは60万円、教育活動60万円で合計120万円がかかる計算になります。
さらに患者離れが起きた分や、院長にかかるストレスなどは全て
プラスαのコストです。
つまり、それらを予防できるのであれば、
月1回4時間のミーティングを充実させることで、
トータルで言えば医院の収支をさらにプラスにする可能性がある
と言えますが、どうでしょうか」
加藤院長はうなずきながら答えた。
「こうやって数値化するとイメージしやすいですね。
数字の精度は改めて見直すとしても、ざっくりとした経済効果の考え方は
つかめた気がします。
重要なのは、それだけの経済効果を生むように、
ミーティングの中身をブラッシュアップすることですね」
【今回のレッスン】
◎ミーティングのように内部充実に充てる取り組みにはコストが掛かっている。
それは実質コストと機会コストの両面から試算してみよう。
◎それだけの経済効果を生むように、ミーティングの中身を
ブラッシュアップすることが重要。
「さらに理解を深めたい人はこちらの記事もオススメ」
▶︎新メニューにおけるスタッフの分配はどうするか?役割の構成比を数値化する!