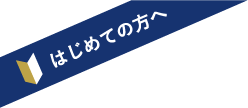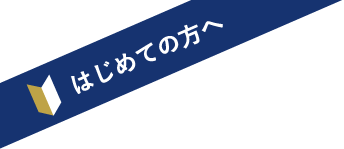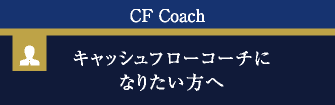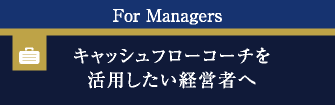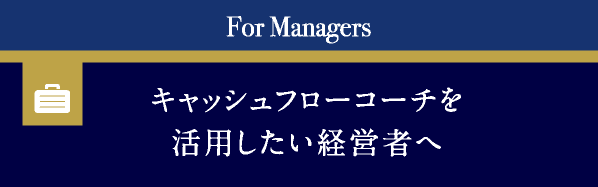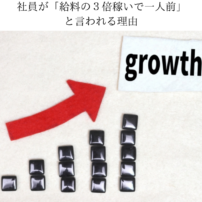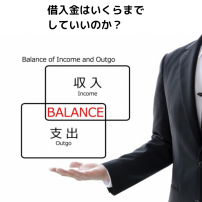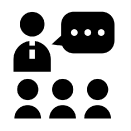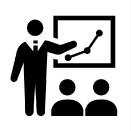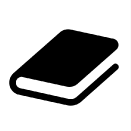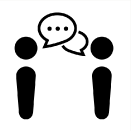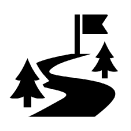「ボーナス金額の決め方を教えて」と 社長に相談された時の対応法は?
2025.05.04 執筆者:和仁 達也![]() キャッシュフロー経営コミュニケーション人件費着眼点
キャッシュフロー経営コミュニケーション人件費着眼点
「クライアントからのお金の相談に、
どのように乗ればよいか?」
という不安を抱えるコンサルタントは
少なくないようです。
そこで、
キャッシュフローコーチ養成塾への参加を
検討中の、コンサルタントで独立を目指す人
から受けた相談を共有します。
「社長から『社員のボーナスの金額の
決め方について教えてください』
と相談されたときに、どう答えて良いか
不安があります。
社員のモチベーションにも関わるので、
「固定給+成果連動式」で払うのが良いのか、
それとも成果に直接変わらない部署の人も
いるので、一律固定にした方が良いのか、
どのように考えるのが良いでしょうか?」
このような相談を受けたときに
【陥りがちな失敗例】を、先に紹介します。
それは、
「御社は営業会社なので、売上に比例して
売上の何%を分配するといいと思います」
「同業他社ではこのくらいのボーナスを
払っているので、これを目安に決めましょう」
「固定でいくら払って、さらに成果に連動させて
+αの歩合を払うと良いでしょう」
「〇〇式報酬制度を導入して、
これに当てはめて決めましょう」
と言うように、1つの型を教えて、
それに当てはめるケースです。
あるいは、
「ボーナスは事務の方は年に2回30万円ずつ。
営業マンには20万円円+歩合で成果の
パーセンテージで払いましょう」
のように、いきなりズバッと
数字で決められるケースもあります。
これって、納得感あるでしょうか?
他社の型を当てはめられても、
会社それぞれに事情が違うので、
違和感があります。
ここでポイントは、
「いきなり具体論でアドバイスされても、
相手は納得しない」
ということです。
大切なのは、
「抽象度高めから入り、
徐々に具体論に落とし込む」
ことです。
これ、具体論でアドバイスする
コンサルタントの気持ちもわかるんです。
たいていの場合、クライアントの社長は
具体的な答えを求めてきますからね。
なので、社長は口では
「(正解を)教えてください」
と言うものです。
それをコンサルタント側が真に受けて、
いきなり具体的な答えを出そうとすると、
そこにズレが生じるわけです。
そもそも、ボーナスの金額を決めるのは、
その会社の業績や方針、ボーナスに対する
考え方などによってそれぞれ違います。
なので、
コンサルタントの過去の事例や主観で
考えてしまっては、
本当にクライアントにとっての
最適解を導いているのか、
アドバイスする側も不安になりますよね。
そこでキャッシュフローコーチ流であれば、
次のように対応します。
相手の相談をそのまま受け止めるのではなく、
【一旦、抽象度上げたところから関わる】
という意思表示を、”前置き”するのです。
「まず大前提のところからお話ししたいのですが、
ボーナスをどのようなものとして捉えているかが
会社それぞれによって異なると思います。
ある会社ではボーナスと言うのは名ばかりで
実質上は給料とほぼ変わらない扱いをしている
ところもあります。
基本給の1.5ヶ月分を夏と冬払うと決めていて、
社員にもそう伝わっているような形です。
この場合、急に成果連動型を取り入れると
社員は混乱するでしょう。
初めからボーナスをあてにして、マイホームの
ローンの支払いに使う予定があれば
そこに影響してしまいます。
その状況の中でボーナスは業績が良かったときの
成果配分なので、次回からバッサリ切り替えます
と言うのは難しいでしょう。
その場合、
『当面はボーナスの大半を固定にしつつ、
1~2割程度を成果連動にする』
と言うように、影響の範囲が小さい形で
徐々に移行すると言う道もありますね。
また、営業社員と事務社員では評価は分かれます。
営業は自分の力で売上を作れますが、
事務の人は売上に直接貢献できない分、
そこをどのような形で評価するのか。
本質的には、
『本来営業マンがやるべき事務作業を
代わりにやってくれるおかげで、
より多くの時間を営業に振り分けられている』
のであれば、営業の成果の一部を
事務の貢献として評価することも必要でしょう。
このように会社の実態によって、
理想的なボーナスの作り方を一緒に
考えていくことが大事なのではないかと
考えますが、いかがでしょうか?」
・・・と、このような話をすると、
たいていの方は
「そりゃ、そうですね。出来合いのものを
ポンと導入してうまくいくものでは
ありませんから。
うちの会社にとっての理想のボーナスの
あり方をこの機会に考えてみたいです」
となるでしょう。
一方で、会社全体の大きな枠組みとして、
「粗利に対して人件費が何%になっているか」
と、”労働分配率”の指標を決めて、
ちゃんと利益が捻出できる収支構造を
整えておくと言うマクロの視点は必要です。
このように、外堀を埋めながら、
具体論を詰めていくことが重要でしょう。
この話は、
「相手が具体論を求めてきても、
具体論で返してはいけない。
抽象度高めのところから入って、
具体論に落とし込むことが真の解決策に
たどり着くカギである」
と言うことです。
「教える」ことに価値の主軸を置かず、
考え方や基準、着眼点を提示しながら
一緒に考え、
納得の結論にたどり着くサポートを
することが、
パートナー型コンサルのスタンスであり、
キャッシュフローコーチの立ち位置です。
コンサルタントとしての関わり方のイメージが
伝われば嬉しいです。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ビジョナリーパートナー 和仁達也
「さらに理解を深めたい人はこちらの記事もオススメ」
▶︎ボーナスを支払うときに悩む理由とは?金額そのものより「どんな意図で決めたのか」を伝える!
■お知らせ:6月開講のキャッシュフローコーチ養成塾の詳細はこちらです。