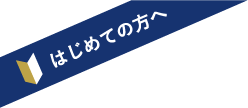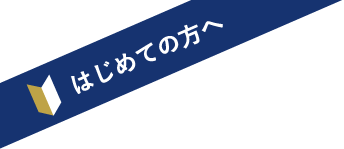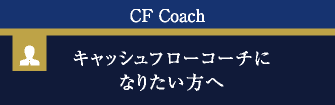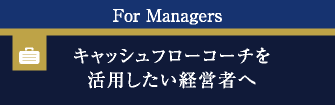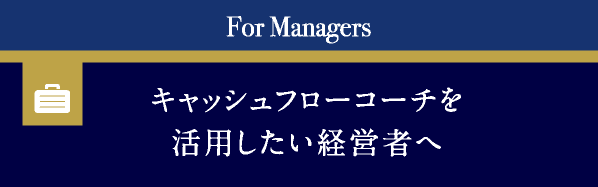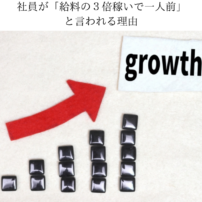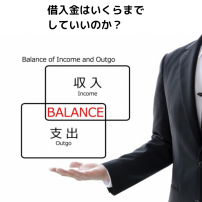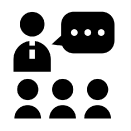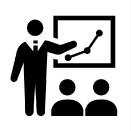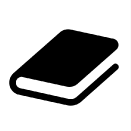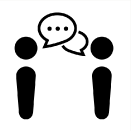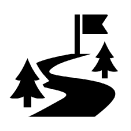感覚派から根拠ある評価にボーナス制度を変えるには?新しい挑戦はスモールステップで始めよう!
2025.05.15 執筆者:和仁 達也![]() キャッシュフローコーチキャッシュフロー経営人件費着眼点
キャッシュフローコーチキャッシュフロー経営人件費着眼点
社員数人の家族経営からスタートした会社が、10人を超えた頃に
顕在化する問題に、「評価の仕方」があります。
「社長の目が行き届きにくくなる」という物理的な側面と、
「会社の発展に自分がどう貢献しているかが見えない」という
社員のモチベーションの側面の両面が、その要因です。
そこで根拠ある評価をボーナスに反映させるときの留意点について、
歯科医院の事例ストーリーで紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半年に1度のボーナスの支給日を前に、加藤院長は
院長室で考え込んでいた。
次のボーナスの支払い方についてのことだ。
スタッフが5人以下の頃は、全員に目が行き届いていた。
よって院長の感覚的な評価は的を射ており、タイムリーに
褒めたり労ったりしていたので、何も問題はなかった。
実際のところボーナスは基本給に基づく固定制で、
数千円程度が院長の評価で上下する程度だったので、
評価の仕方についてスタッフから異議の声が上がることもなかった。
しかし、スタッフが10人を超えてきたあたりから、
ボーナスの支払い方やその評価の仕方について不満の声が出始めてきた。
「院長はちゃんと私たちを見てくれているのか?」
「どう頑張ればボーナスとして評価されるのか知りたい」
と言うものだ。
加藤院長としても、いつまでも自分の感覚的な評価に頼るのではなく、
そろそろ一定の根拠に基づいた評価に変えていくべきだと思っていた。
またスタッフの仕事ぶりや活躍の度合いにも差が
つき始めていたので、ボーナスに差がないことが
逆に不公平なのではないかとも感じ始めていた。
そこで今月のキャッシュフローコーチの和仁との定例ミーティングでは、
「根拠ある評価に基づくボーナス制度を取り入れるには?」
のお題を取り上げることにした。
キャッシュフローコーチは院長の話を一通り聞くと質問を投げかけた。
「加藤院長、ボーナスの評価について不満の声が出ているとの事ですが、
それは何人、つまりスタッフの何%の人が言っているのでしょうか?」
その質問の意図は、発言者の声の大きさに気をとられて、
実は少数の人間が言っているに過ぎないことを
スタッフ全員の声と捉えてしまい、かえって多数のスタッフから
違和感や反発を招くことがないようにしたい、との思いからだった。
この点は、特定の1人や2人と言うわけではなかった。
場面こそ違えど、3人以上のスタッフが自分たちの
評価のされ方について気にしている発言があったことから、
少なからぬスタッフの意見と捉えて良さそうだった。
キャッシュフローコーチはうなずくと話を続けた。
「わかりました。ホワイト歯科のように、これまで仕事の仕方で
大きな差がつかないボーナスの支払い方をしていた医院が、
仕事の成果や取り組み方で評価して金額に差をつける制度に
変更するときに気をつけたいポイントが3つあります。それは、、、」
そう言うと、キャッシュフローコーチはホワイトボードに書き始めた。
1)ボーナス総額の決め方
2)評価する項目の言語化
3)固定額と変動額の構成比
「順番にお話ししますね。まず大前提としてスタッフの生活費として
一定額の支給が約束されている給料とは違い、
ボーナスは本質的には成果分配です。
つまり医院に相応の利益が生まれたときにそれをスタッフに分配するものです。
したがって、もし医院に十分な売上や粗利が確保できておらず、
大幅な赤字になった場合には、支払いたくても支払えないことも
あるわけです。もちろんそうならないように医院全体として
努力するのは大前提ですけどね。
例えば、医院の業績が厳しい中でスタッフにボーナスを
支払ったら大赤字となり、銀行の評価が下がって借り入れができず
医院が倒産してしまったら元も子もないですよね。
なので、スタッフ一人ひとりにいくら支払うかを考える前に、
総額としてのボーナス原資をいくらにするかをまず決める
必要があります。
それは普段お話ししている通り、粗利の何%を人件費に振り分けるのか
と言う労働分配率に基づいて決めていくことになります。
ホワイト歯科はこの点は明確に基準があるから大丈夫だと思います。
次に考えたいのは、評価項目の言語化です。
加藤院長はスタッフのどのような点について
ボーナスの評価基準として重要視していますか?」
加藤院長はこの点については考えを持っていた。
1)院内のホウレンソウ(報連相)
2)患者さんへの対応の仕方
3)院内の「安心安全ポジティブな場づくり」への貢献
4)スキルアップの努力
5)日ごろの勤務姿勢
「この5つについて評価したいと思っています。
今書き出してみて気がつきましたが、今まではこの5つの項目すら
明確にせず、もっと感覚的に評価していました。
しかしこの5つの項目をもとに点数化すれば、
より根拠ある評価にできそうな気がします。
ただ不安なのは、いきなりボーナスの仕組みを変えてしまって良いのか、
と言う点です。
それによってボーナスの支給額が大きく変わる人がいた場合、
それが不満となりモチベーションが下がってしまうのではないか
という不安もありますし、そもそも私がどこまで正確に評価できるのか、
という私側の不安もあります」
院長の意図を汲み取るとキャッシュフローコーチは続けた。
「加藤院長の不安な気持ちはよくわかります。
特に新しい挑戦はいきなり始めるとその波及効果はよくも悪くも
大きくなりますからね。
かと言ってそれを過剰に恐れると、何も始まりません。
そこでわたしのオススメは、
新しい挑戦はスモールステップで始めることです。
“小さく始めて大きく育てる”作戦が精神的なストレスを
最小化してくれて、新しい試みに加速をつけてくれます。
今回のことで言えば、はじめは院長評価の割合を小さくしておく
のはどうでしょうか。
例えばボーナス総額の1割だけを院長の評価に基づくものとして、
残りの9割はこれまでと同じにするのです」
加藤院長はうなずきながら答えた。
「その程度であればスタッフのみんなも抵抗感なく
受け入れてくれると思います。
また多少なりとも評価が反映されていることで、
自分たちの頑張りや努力が報われる気持ちにもつながると思います。
そして徐々に評価の割合を高めていけばいいんですよね」
キャッシュフローコーチは笑顔で答えた。
「そうです。評価する側も評価される側も、これははじめての試みですよね。
そのような時は、その影響力が大き過ぎることがないよう、
小さく始めて雪ダルマ式に徐々に大きくしていくことがお勧めです。
毎回のボーナスのたびに改善点を重ねていけば3年後、5年後には
今とは違うよりホワイト歯科にふさわしいボーナス制度が
出来上がっているのではないでしょうか」
小さく始めて大きく育てる。昔からよく聞く言葉だが、
その言葉の重みを噛み締めながら加藤院長は次のボーナスの方向性を心に決めた。
【今回のレッスン】
◎固定性だったボーナスを、スタッフの仕事の成果や取り組み方で評価して
金額に差をつける制度に変更するときは「ボーナス総額の決め方」
「評価項目の言語化」「固定額と変動額の構成比」の3つに留意する。
◎新しい挑戦はスモールステップで初めて、雪ダルマ式に大きく育てる。
「さらに理解を深めたい人はこちらの記事もオススメ」
▶︎給料の決め方、考え方。世間で言われている目安は本当なのか。